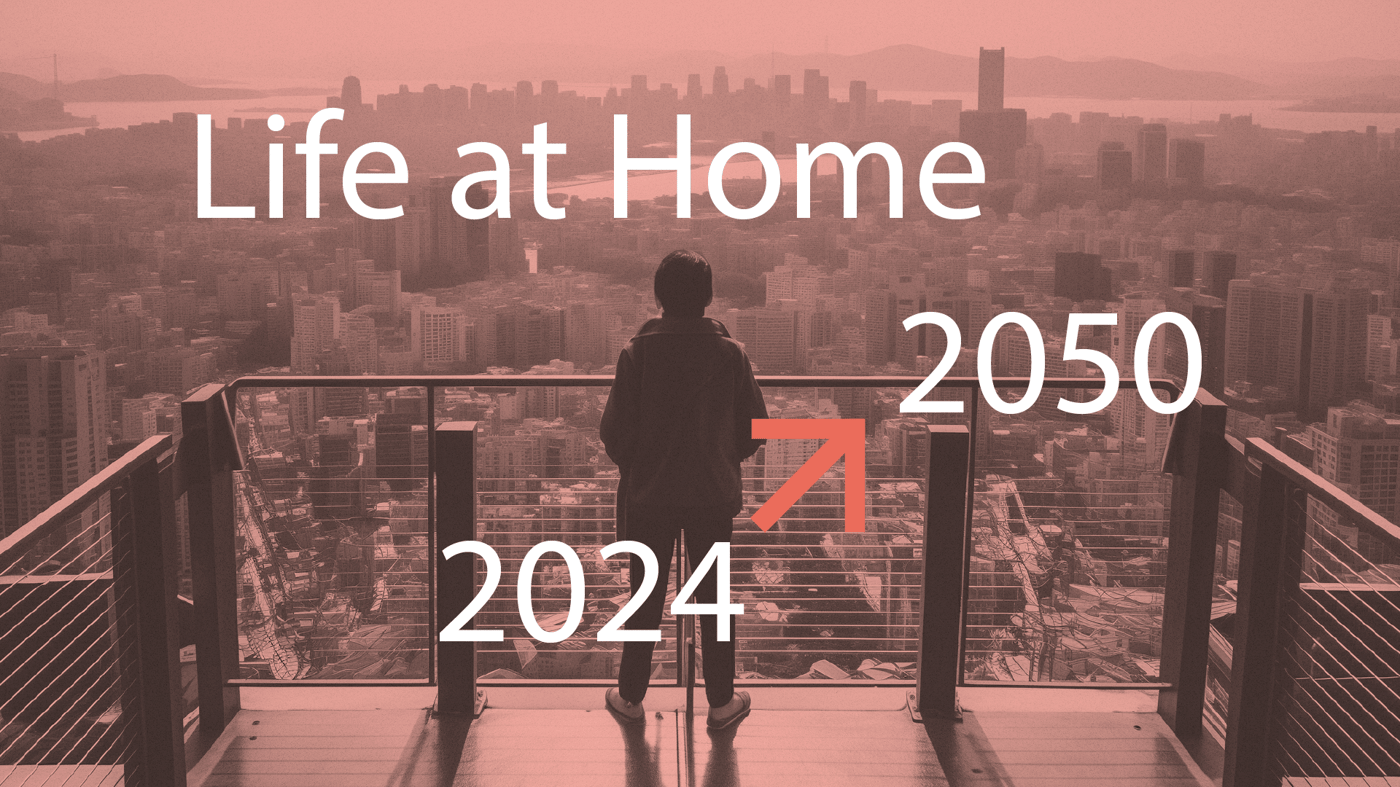家での暮らしに喜びを
毎年イケアは世界中の人々に話を聞き、今の家での暮らしには何が重要で、それをさらによりよくするためにイケアがどのようにお手伝いできるかを把握する取組みを行っています。それがイケアの「 Life at Home Report」です。
今年の調査では、家で楽しさを見つけることが、私たちをより幸せで前向きにする一方、3人に1人以上は十分に楽しさを体験していないことがわかりました。
イケアは、家でのより楽しい瞬間は、手の届くところにあると信じています。お金をかける必要はなく、シンプルかつお手ごろにできること、充実した時間から得られるものです。

「家がサステナブルな暮らしを可能にすると答えた人の63%*は、家がお気に入りの居場所であると答えています。 」
よい環境でウェルビーイング
自分の周りにあるものとの関係を大事にすると、ウェルビーイングにすばらしい効果をもたらします。住むところ、職場、または遊ぶための環境は、いつも選べるわけではありませんが、大切なのはその中で自分でできる小さな取組みや選択です。
昼寝は大事
イケアの調査では、家でウェルビーイングを育む上でもっとも重要なのが睡眠だということがわかっています。8時間の睡眠でも、5分間のうたた寝でも、またはベッドの上でダラダラする午後でも、心地よい気分で過ごすにはベッドがつねに頼りになります。
心地よい眠りに役立つ商品をチェック
「たった14%の人々しか『家が遊び心を引き出してくれる』と感じられていませんが、家で遊びを体験する人の61%*は未来について前向きです。」
家の大きな影響力
楽しさ、創造性、遊びをもう少し増やすと、日常がもっと活気あるものになります。意識的な選択をして、自分の中に埋もれている子どもの時に感じたような喜びを再発見しましょう。子どもに戻ったみたいに遊んだり、モノづくりを楽しむ準備はいい?あなたならできます!
「個性を大切にすることが、帰属意識を育みます。家に帰属意識が感じられ、かつ自分のアイデンティティを家に表現できている人の57%*は、家で楽しみを頻繁に体験しています。」
自分を映し出す家
自分が住む場所に帰属していると感じられることは、家を楽しむことの本質的な部分です。オブジェ、細部へのこだわり、気分が上がる鮮やかな装飾、または心を落ち着かせる自然を感じられるデザインなど、「自分らしさ」を感じさせる小さなものが効果を発揮します。お好みのスタイルがどんなものでも、家のあらゆる場所のためのインスピレーションあふれるアイデアが見つかります。
インスピレーションあふれる部屋のアイデア
「食事を社交的なアクティビティとみなしている人の69%*は、家での暮らしが幸せであると感じています。」
食事を囲んで集まる
おそらくそうだろうと気づいるかもしれませんが、食事は人々を結び付ける磁石のような存在だということが調査でわかりました。一緒に食事をするとしても、料理をするとしても、食べ物は話題のきっかけになりやすく、礼儀正しい日常会話から入り、意義のある話へと深めるのにも役立ちます。さらに、それをくつろいだ雰囲気の家で楽しめます。

- 商品情報ページ




イケアの「Life at Home Report 2024」のご紹介
最新のLife at Home Report「家での暮らしに喜びを」について詳しく知りたいですか?もしそうなら、このページは始まりにすぎません。次のステップは、どれくらい深く知りたいかによって異なります。
レポートを読む
今年のレポート全文を読みたい?こちらでダウンロードして、より詳しい内容をゆっくりお楽しみください。
仕事も趣味も、自分らしく過ごせる部屋に
イケアコワーカーの部屋を大改装!カスタマーサービスに所属するコワーカーの部屋を大改装しました。仕事も趣味もエンジョイできる空間に変えたことで、生活の質が向上しました。
Life at Home 2050
「家」から考えるジェンダー平等
「平等・公平は家から始まる」と私たちは考えます。では、平等・公平を実現した世界とは、どんな世界でしょうか? まずは一緒に想像してみましょう。